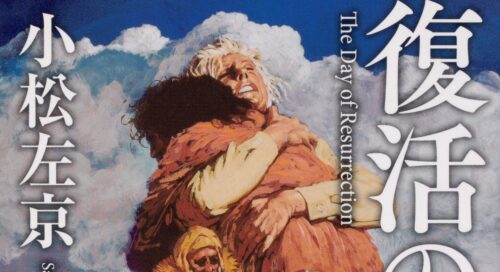
こんにちは、認知症パパを介護中のユウコ姉です。
介護は確かに大変だけど、ココロにスキマを作ってあげて、上手にストレス解消しましょうね!

知人に勧められて読んでみました。小松左京は初トライ
【復活の日】について
今『復活の日』が改めて注目を集めています。
半世紀前すでに、コロナ禍を予言するかのような人類最大の危機を描いた小説だからです。
そこには次のような環境問題や大災害が記されています。
*********
35度を超える猛暑。
例年より早い梅雨入りと長雨。
世界各地で起こる地震。
そして、インフルエンザの一種かと思われていた“肺をやられる風邪”があっという間に蔓延し、ワクチンも効かず死者の山を築いていく・・・
*********
1964年に発表された小説ですよ!?
温暖化による地球規模の災害を予測し、まるで新型コロナを題材にしたかのような作品です。
各国の政府筋の考え方や対応も、現在とほぼ変わりがなく、笑いごとではない展開。
今だからこそ、多くの人が読むべき小説ではないかと思いました。

あらすじ
1982年、ドイツの研究所から盗まれた猛毒ウイルスは、輸送機の墜落によって、その存在を知られる前に生き物の間で拡散していき、気づいた時には世界中が壊滅するほどの打撃を受けていました。
最終的に生き残ったのは、南極観測員を中心とした約1万人のみ。
彼らは2隻の原子力潜水艦を駆使して各地を監視しながら、規律正しい行動でなんとか生き延びましたが、地質学の専門家・吉住が大規模地震を予測することで事態は一変。
人類滅亡を防ぐために吉住を含む二人の隊員が犠牲覚悟で北米に向かうのですが・・・。
作者の小松左京氏について
小松左京。
あまりにも有名な日本が誇るSF作家なのに、私は今まで一度も読んだことがありませんでした。
いや、あえて読もうとしなかった・・・というのが正しいかも。

想像力が具体化して、眠れなくなりそうでしょ?
そんなわけで『日本沈没』も『復活の日』も、映画さえ見ていません。
杖をつき、ボロをまとって彷徨う主人公のポスターは覚えていますけどね。(^^;
けれど先日、知人が「他国で大勢のコロナ死者が出て一気に火葬する様子を見て、昔読んだ『復活の日』を思い出した」と聞いて、今さらですが「読んでみよっかな」と思ったのでした。
小松左京 Sakyou Komatsu <Profile>
- 1931年、大阪生まれ、新制京都大学文学部(イタリア文学専攻)を卒業。
- 1962年、経済誌記者、放送作家を経て、SFマガジン誌にデビュー
- 以後『復活の日』『果しなき流れの果に』『日本沈没』などを次々と発表し、日本推理作家協会賞他数多く受賞
- 2011年、死去

小松左京【復活の日】のあとがき
私は電子書籍を購入して読んだので、1964年初版のあとがきや、文庫用1980年版のあとがき、最近の解説などが巻末に載っていて、当時の作者の思い、今現在のこの小説の立ち位置などの理解が深まった気がしました。
以下、左京氏の初版あとがきです。
20世紀後半どころか、21世紀の今でも十分通じる考え方に共感できます。
偶然に翻弄され、破局におちいる世界の物語を描いたところで、私が人類に対して絶望していたり、未来に対してペシミスティックであると思わないでいただきたい。逆に私は、人類全体の理性に対して、――特に二十世紀後半の理性に対して、はなはだ楽観的な見解をもっている。さまざまな幻想をはぎとられ、断崖の端に立つ自分の真の姿を発見することができた時、人間は結局「理性的」にふるまうことをおぼえるだろうからである。 ~昭和39年・初版あとがきより
また、小説の構想を練っている段階でかかってきたという編集長との電話の内容が面白いです。
『破局テーマで行きます。・・・ええ、細菌戦もの・・・」と答えてしまった。“核戦争以外の破局テーマ”という事で、頭の隅に何かあったのかもしれない。
「いいでしょう・・・」と福島さんはいった。「で、題はきまりましたか?」
「ええと・・・“復活の日”としておいてください」
~角川文庫『復活の日』(1980年版)あとがきより
『復活の日』・・・これ以上ない最高のタイトルなのに、電話しながらなんとなく決まったらしい(笑)。
天から降りてきたのかもしれませんね。
【復活の日】今日のまとめ
今回、初【左京】に挑んだ私ですが(笑)、やっぱり読んで怖かったです。(><;
でも続きを読まずにいられない劇的な展開で、2日くらいで読み終えました。

世界的大流行=パンデミック(文中では“パンデミー”)という言葉が出てきてドキッとします
初めて読む私は、本当に50年以上前の作品なのかと疑ったくらいです。
決してSFが苦手ではないし、10代の頃には友達と一緒に、筒井康隆や星新一を読んだものだけど、やっぱり小松左京は別格っていうか、知識の幅広さ、奥深さが尋常じゃありませんね。
しかも専門知識をわかりやすく記述してあるのが、またスゴイ!

アーサー・C・クラークなんて、難しいものね
私のように敬遠してきた方も、以前読んだという方も、今読むに価する小説だと思います。
機会があったら、ぜひどうぞ!
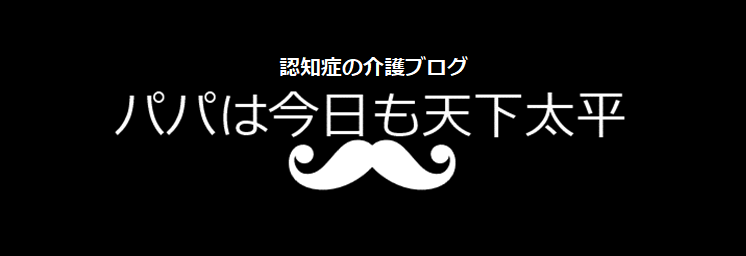
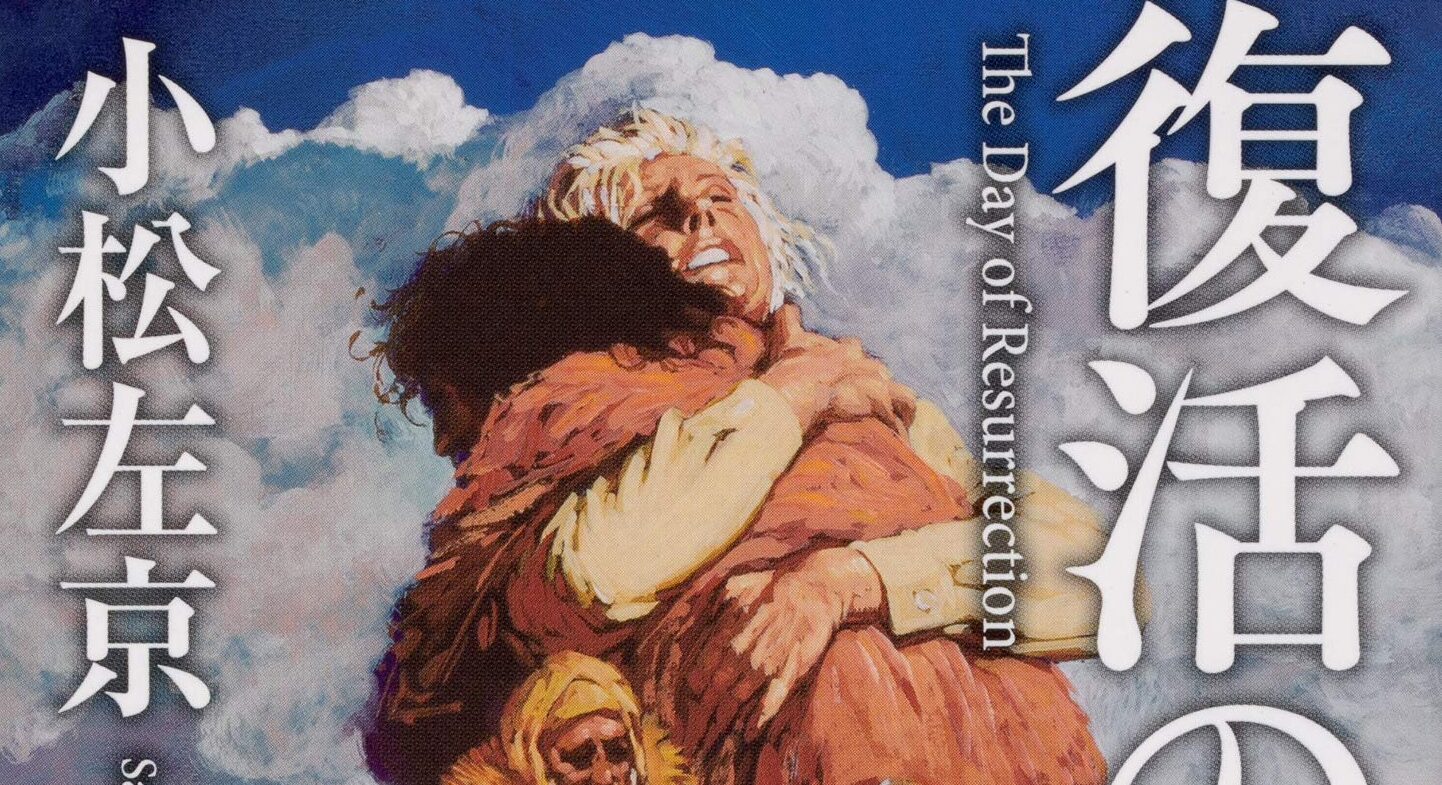


コメント