
こんにちは、認知症パパを介護中のユウコ姉です。
介護は確かに大変だけど、ココロにスキマを作ってあげて、上手にストレス解消しましょうね!

3度目なのにまた泣けた・・・何回読んでも感動します
【楽毅】について
私が楽毅(がっき)という人物を知ったのは、書道の課題で『楽毅論』について書いた時。
『楽毅論』は三国時代の魏の夏侯玄(かこうげん)による人物評ですが、書聖・王羲之(おうぎし)の書いた作品が有名です。
王羲之が好きな私は楽毅にも興味をそそられ、調べるうちに宮城谷さんの小説に行きついたのでした。

作家の宮城谷昌光さんについて
宮城谷氏の小説は、三国志よりもはるか昔の古代中国の英雄を取り上げたものが多いですよね。
私は『管仲』(かんちゅう)など他の小説も何作か読みましたが、これから『三国志』に取りかかるところです。曹操の祖父の時代から始まる息の長~いお話みたいで、いつ読み終えるかわかりません(笑)。
宮城谷昌光 Masamitsu Miyagitani <Profile>
- 1945年愛知県生まれ、早稲田大学第一文学部英文科卒
- 1991年『天空の舟』で新田次郎文学賞、『夏姫春秋』で直木賞
- 1993年『重耳』で芸術選奨文部大臣賞
- 2000年、司馬遼太郎賞を受賞
【楽毅】 内容
古代中国の戦国時代、小国・中山(ちゅうざん)の宰相の息子として生まれた楽毅は、見識を広めるために敵国・斉に留学し、幸運にも天下の実力者・孟嘗君(もうしょうくん)に謁見したことで衝撃を受け、己の生き方が大きく変わっていきます。
忠義を尽くそうにも、中山は暗君によって傾き、三代に渡る王を支え続けたものの国は滅亡、やがて燕の昭王に請われて、ようやく楽毅の能力と名は世の中に知れ渡るようになりました。
そんな中、斉王に恨みをもつ昭王を助け、楽毅は大国・斉に戦いを挑みます。
燕が斉に大勝するという偉業を成し遂げた楽毅でしたが、志半ばで死去した昭王の後を継いだ恵王に疎まれ、妻子を残したまま趙に逃れることになるのでした。

【楽毅】の魅力
『楽毅』という小説の中には、主人公以外にも魅力的な人物がたくさん登場します。
彼を愛する家族や家臣、楽毅の能力に敬服する敵方の将軍、楽毅を導く孟嘗君や、楽毅を「千里の馬」と称えた燕の昭王、最後に楽毅を招聘する趙の恵文王・・・それぞれの人物がみな情に厚く思いやりがあって、読んでいるこっちまで胸が熱くなるんです。
夏侯玄が『楽毅論』を書いたのは、楽毅が斉を攻めた際、二城を落とし損ねたことで過小評価されている楽毅の功績を再び称えるためだったそうですが、
そこに楽毅の素晴らしさが凝縮されています。
孫氏の兵法を学んだ楽毅は「勝敗は戦う前に決まる」ことを前提に、あらゆる戦術を駆使して味方の損害を最小限にとどめました。
死を美化せず、人を生かすことを優先する武将だったからこそ、私たちを感動させてくれるのだと思います。
【楽毅】今日のまとめ
この物語の中には、何度も『管仲』の話が出てきます。
その管仲が気になって、私は『楽毅』を読んだ後すぐに『管仲』を買って読みました(笑)。

『孟嘗君』にしようと思ったんだけど、メチャ長いし
「楽毅は管仲に並びうる」こんな言葉が再々出てくるのですが、それは楽毅が軍事に優れているだけでなく、内政や外交にも人並外れた才能を発揮したから。
また孟嘗君と同じように敵味方という損得ではなく、天下を俯瞰して人を生かす術を模索する生き方に、あの孔明も魅了されたそうですよ。

心に響く名フレーズ
ホントに最初から最後まで、エンターテインメント性にあふれた小説なのですが、私が特に好きな文章を少しピックアップしてみました。
中山最後の王が仲間と共に潔く散りたいと望んだ時、楽毅が王を諫め、再起を果たすように諭す場面~
楽毅は戦って死ぬことを考えない。戦って生きるのであり、生きるために戦うのである。戦いは進路がすべてであるといってよい。それゆえ、生きることも進退なのである。美しさがあるとすれば、進退にこそある。その進退を生死にすりかえてしまえば、人はおわりであり、あえていえば、死ぬまえに死んでいる。(第3巻「炎の塞」より)
楽毅の配下となった恵泛が、若輩の楽乗に楽毅を評して「楽将軍のもとにいると正常でいられる」と言う場面~
「不敬なことをいいますが、楽将軍の戦術と戦略には、遊びがある。その遊びが、わたしを救ってくれるのだと気づきました」
「人が十の力を十出せば死ぬ。楽将軍は八でとめる。それにもかかわらず、敵が楽将軍をみれば、十以上の力を出しているようにみえる」(第3巻「滅亡の日」より)
斉を追われ魏にやってきた孟嘗君が自ら楽毅の家を訪ね、涙しながら楽毅を褒めたたえる場面~
「わしが斉にいるあいだ、将軍は中山で戦っていた。中山王は斃死せず、中山の民は熄滅(そくめつ)しなかった。それが中山をあずかっていた将軍の愛の表現であると、わしは臨̪淄にいて考えていた。将軍は、まことによくなされた。みごとであったとたれも褒めぬのであれば、ここでわしが天にとどくほどの声でほめよう」 (第4巻「再会」より)
この文章だけを読んでも響くものはないかもしれませんが、ここまでの苦労を読んできた私は、孟嘗君のやさしさに感激して一緒に泣いてしまうのです(笑)。
宮城谷氏の『楽毅』を読んだおかげで、私の歴史小説の世界が広がりました。
歴史小説が好きな方に、ぜひお勧めします!
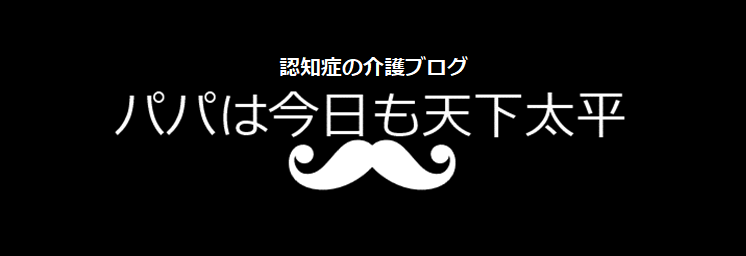


コメント